
不動産を売却するとき、「減価償却って何?」「売却益の税金はどう計算されるの?」と不安を感じる方は少なくありません。特に気になるポイントは以下のような点です。
- 建物の価値が減ると売却時の税金はどうなるのか
- 減価償却は譲渡所得にどのように影響するのか
- 節税できる特例や控除はあるのか
この記事では、不動産売却時に関わる減価償却の仕組みと、譲渡所得・税金との関係を整理して解説します。さらに、3,000万円特別控除や軽減税率といった節税策も紹介し、余計な負担を避けるための基礎知識を得られる内容になっています。
目次
減価償却とは?不動産売却で重要な理由
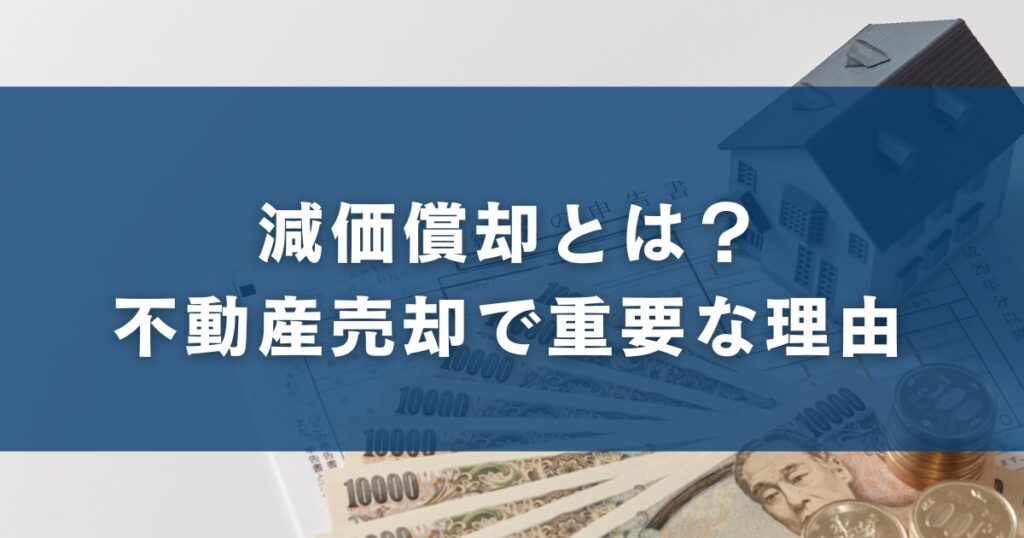
不動産を売却するとき、多くの方が驚くのが「思ったより税金が高い」という点です。その背景にあるのが減価償却です。
減価償却とは、建物などの固定資産が時間の経過とともに価値を失うことを、毎年少しずつ費用として計上していく会計上の仕組みを指します。例えば木造住宅なら22年、鉄筋コンクリート造なら47年といった法定耐用年数が定められており、その年数に応じて資産価値を少しずつ減らしていきます。
減価償却と税金の関係
ここで重要なのは、減価償却の対象は建物であり、土地は減価償却できないという点です。土地は時間が経過しても基本的に価値が減らないとみなされているため、減価償却費を計上することはありません。
不動産売却において減価償却が重要となるのは、売却益の計算に直結するからです。減価償却を行うと取得費が減り、その分譲渡所得が大きくなるため、結果的に税金が増える可能性があるのです。
不動産売却と譲渡所得の関係
不動産を売却したときの利益(または損失)は「譲渡所得」として計算されます。基本的な計算式は以下のとおりです。
譲渡所得 = 譲渡価格 −(取得費+譲渡費用)
ここで「取得費」が減価償却によって影響を受けます。建物の取得費は購入価格から減価償却費を差し引いた金額として扱われるため、所有期間が長くなるほど減価償却費が積み重なり、結果として取得費が小さくなってしまいます。
その結果、同じ売却価格であっても、保有期間が長く減価償却が進んだ不動産ほど譲渡所得が大きくなり、課税される所得税・住民税の負担も増えるのです。
あわせて読みたい


不動産売却における譲渡所得とは?計算方法と節税の仕組みをわかりやすく解説
不動産を売却するときに避けて通れないのが「譲渡所得」にかかる税金です。仕組みを理解していないと、思わぬ税負担に驚くことも少なくありません。 譲渡所得とは何かを…
減価償却累計額が譲渡所得を押し上げる仕組み
減価償却を行うと、建物の帳簿価額(取得費)は次第に減少していきます。例えば新築時に建物部分の取得費が2,000万円だった場合、10年間で累計400万円の減価償却を行えば、帳簿価額は1,600万円となります。この1,600万円が売却時の「取得費」となり、残りの400万円は「減価償却累計額」として差し引かれるのです。
結果として譲渡所得は大きく計算され、税負担が増える要因となります。
数値例で理解する減価償却と譲渡所得
具体例で見てみましょう。
- 建物取得費:2,000万円
- 土地取得費:1,000万円
- 合計取得費:3,000万円
- 所有期間:10年
- 法定耐用年数:47年(鉄筋コンクリート造)
- 売却価格:3,500万円(建物・土地合計)
この場合、建物の減価償却費は以下のように計算されます。
2,000万円 × 0.022(償却率) × 10年 = 約440万円
したがって、建物の帳簿価額は 2,000万円 − 440万円 = 1,560万円となります。
これに土地の1,000万円を加え、売却時の取得費は合計2,560万円です。
譲渡所得は以下の通り。
3,500万円 − 2,560万円 = 940万円
この940万円が課税対象となり、さらにここから特別控除や必要経費が差し引かれます。
もし減価償却を考慮しなければ取得費は3,000万円のままなので、譲渡所得は500万円。つまり、減価償却によって課税対象額がほぼ倍近くになるのです。
減価償却(または「減価の額」)の計算方法と耐用年数の考え方
不動産の建物は時間の経過で価値が減るため、税法上の取扱いは次の2通りに分かれます。
A.賃貸・事業用(=日々の損益計算で使う「減価償却費」)の場合
- 原則:定額法(建物・建物附属設備は定額法が原則)
- 計算式(年額のイメージ)
減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率 × (使用月数÷12) - 「定額法の償却率」は耐用年数に応じて決まります。
- 中古取得の場合は、耐用年数を見直し(簡便法など)したうえで償却率を求めます。
例:簡便法の一例(建物)
見直し耐用年数 ≒(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数×0.2(下限あり)
例:RC造(法定耐用年数47年)の賃貸マンションを取得した場合、
その年の使用月数に応じて、上式で年額を月割して計上します。
B.自宅など非業務用(=譲渡時に取得費から控除する「減価の額」)の場合
自宅など非業務用の建物を売却する際は、日々の損益計算はしていなくても、譲渡所得の計算上、建物の取得費から「減価の額」を控除します。
この「減価の額」は、Aの“定額法の年次償却費”とは計算ルールが別です。
- 基本式
減価の額 = 取得価額 × 0.9 × 旧定額率 × 経過年数
(※月割あり/累計上限=取得価額の95%) - 旧定額率:耐用年数の1.5倍を基礎とする旧定額法の償却率(国税庁の率表を参照)
- 経過年数:取得から譲渡までの期間を月単位で按分(6か月超=1年、6か月以下=切捨て等の実務運用に注意)
例:
建物取得価額が2,000万円、RC造(法定耐用年数47年)を10年保有して売却する場合、
減価の額=2,000万円 × 0.9 ×(RC47年に対応する旧定額率)× 10年
→ この減価の額を建物取得価額から差し引き、土地の取得費を合算して譲渡時の取得費を求めます。
※数値は旧定額率の表・月割・上限95%を踏まえて確定します。
(参考)中古の取り扱い
- 賃貸・事業用で中古建物を取得した場合:まず見直し耐用年数を算定し、その年数に対応する定額法率でAの式を適用。
- 非業務用(自宅など)で中古建物を売却する場合:Bの「0.9×旧定額率」に基づき、取得から譲渡までの経過年数を月割して減価の額を算定。
不動産売却時にかかる税金と減価償却の関係
不動産を売却したときに課される主な税金は、所得税・住民税・復興特別所得税です。これらは譲渡所得の金額に基づいて課税されます。
所有期間による税率の違い
不動産の所有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分けられ、税率が異なります。※判定日は譲渡年の1月1日現在の所有期間。復興特別所得税は2037年(令和19年)まで加算。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下)
→ 税率39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%) - 長期譲渡所得(所有期間5年超)
→ 税率20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)
つまり、同じ売却益でも所有期間によって税負担が倍近く違うのです。
減価償却による税額への影響
減価償却が進むと譲渡所得が増え、課税対象額も大きくなります。例えば前半で紹介した事例のように、取得費が減少することで課税所得が数百万円増えるケースもあります。
これは特に長期保有のマンションや一戸建ての売却時に顕著で、建物部分の価値がほぼゼロに近づき、売却代金のほとんどが譲渡所得とみなされることも珍しくありません。
節税に活用できる特例・控除制度(2025年版)
居住用の不動産を売却する際には、税負担を軽くできる複数の特例があります。どの制度も適用要件が細かく、また他の特例との併用可否が結果に大きく影響します。まずは全体像をつかみ、次に自分のケースに当てはめて選択肢を絞るのが得策です。なお、所有期間の判定は譲渡年の1月1日現在で行われ、復興特別所得税の加算は2037年まで続く点も最初に確認しておきましょう。
居住用財産の3,000万円特別控除
マイホームの売却で譲渡益が出た場合、最大3,000万円まで譲渡所得から控除できる制度です。
たとえば譲渡所得が940万円なら、この特例だけで課税対象をゼロにできます。親子・配偶者など特別関係者への譲渡では使えないなどの制限はありますが、満たせば最優先で検討したい柱となります。
さらに、長期所有住宅の軽減税率(10年超)とは併用可能で、控除により課税所得を圧縮した上で、残額に軽減税率を適用することもできます。一方で、買換え特例や居住用の譲渡損の通算・繰越と同時に使えない組み合わせがあるため、どれを選ぶかは事前の試算が欠かせません。
長期所有住宅の軽減税率の特例
居住用不動産を10年以上所有して売却した場合、長期譲渡所得に軽減税率が適用されます。
課税対象額のうち6,000万円以下の部分は14%(所得税10%+住民税4%)、6,000万円を超える部分は20%(所得税15%+住民税5%)となり、通常の長期20.315%よりも負担が下がります(いずれも復興特別所得税は別途加算)。
この特例は3,000万円特別控除と併用可能で、まず控除で譲渡所得を減らし、残った金額に段階的な軽減税率をかける、という順序で効果を最大化できます。
買換え特例
マイホームを売却して一定要件を満たす新居を取得する場合、譲渡益への課税を後日に繰り延べできる制度です。誤解されがちですが非課税ではなく“繰延べ”であり、将来その資産を売却すると繰り延べた益も含めて清算されます。
適用期限は2025年12月31日まで(現行)で、適用範囲や面積・居住要件など細かな条件があります。大きな課税を当面回避したいケースで有力ですが、3,000万円特別控除や軽減税率とは原則併用できないため、どちらがトータルで有利かを複数年視点で比較検討してください。
損益通算と繰越控除
売却で損失が出た場合でも、居住用に限り一定の要件を満たせば、給与等の他の所得と相殺(損益通算)したり、相殺しきれない損失を最長3年間繰り越して控除できます(代表例:買換え等のケースや、住宅ローン残高がある状態での売却損など)。
一方、一般の不動産(居住用以外)の譲渡損は原則通算不可です。また、この特例は3,000万円特別控除や買換え特例と同時に使えない組み合わせがあるため、適用順序や選択の是非を事前に確認しましょう。
得かどうかは試算がカギ!
同じ「得」でも、(1)3,000万円控除+軽減税率で“今”の税額を下げる方法と、(2)買換え特例で“将来へ課税を繰り延べる”方法とでは、ライフプランや保有予定年数、価格見通しによって結論が変わります。概算でも3パターン以上の試算を出してから選ぶのが安全です。
減価償却を理解して不動産売却時にトラブルを避けるポイント
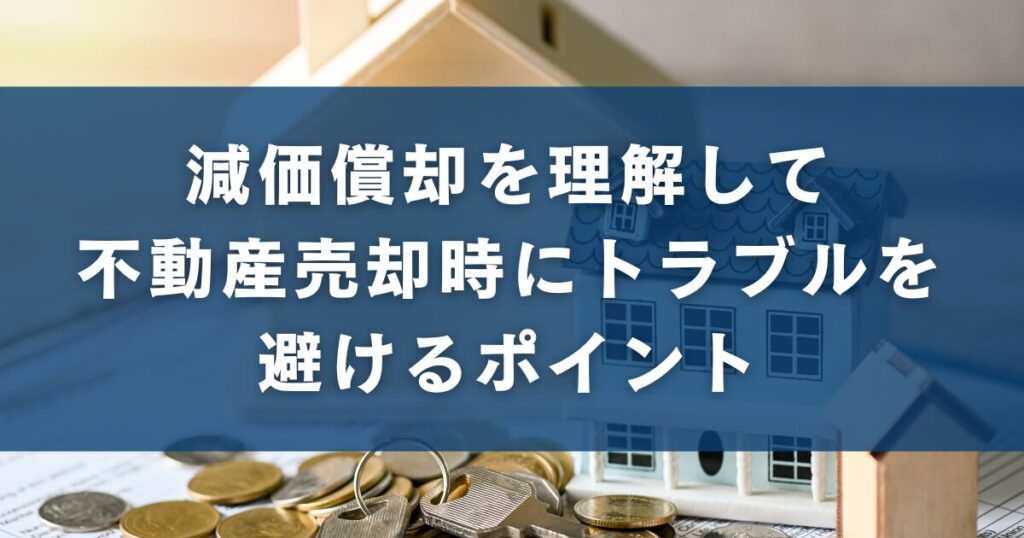
減価償却と税金計算は複雑で、ちょっとした認識の違いが大きなトラブルに発展することがあります。以下のポイントを押さえておきましょう。
- 契約書に建物価格を明記すること
契約書に建物と土地の価格を分けて記載しないと、税務署から取得費の根拠を求められます。建物価格が不明な場合、「概算取得費(売却価格の5%)」しか認められないケースもあり、結果的に税負担が増える可能性があります。 - 確定申告時の必要書類を準備すること
売買契約書、登記事項証明書、固定資産税評価証明書などを揃えておくと、取得費の証明がスムーズです。 - 税理士や不動産会社への相談
減価償却累計額の算出や耐用年数の判定など、専門知識が必要な部分は専門家に依頼するのが安心です。特に高額取引では、数十万円単位の節税効果が得られることもあります。
あわせて読みたい


不動産売却の税金とは?計算方法・税率・特別控除・確定申告などを解説
不動産を売却すると、想定外に税金がかかり資金計画を狂わせてしまうことがあります。 どんな税金がかかるのか分からない 税率や計算方法が難しく不安 節税できる方法を…
まとめ
不動産売却において減価償却は、譲渡所得と税金を左右する大きな要素です。
建物の取得費は年々減少し、その分譲渡所得が大きく計算され、結果的に税負担が増える仕組みになっています。しかし、居住用財産の3,000万円特別控除などの特例を活用すれば、大幅な節税も可能です。
不動産売却を検討している方は、減価償却と税金の関係を正しく理解し、余計な税負担やトラブルを避けるためにも、早めに専門家へ相談することが安心への第一歩です。

