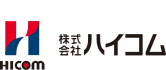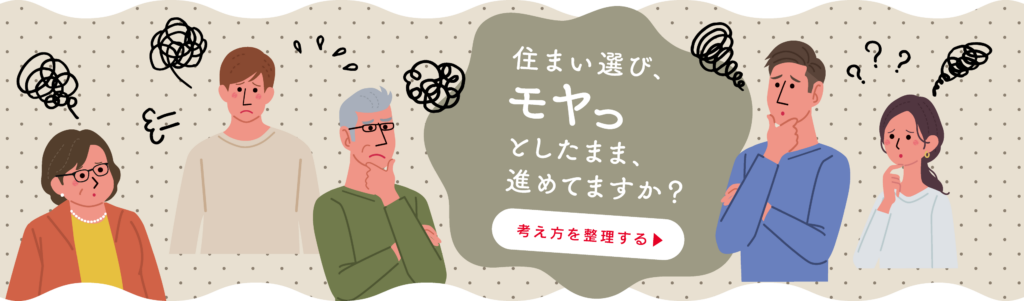
不動産売却には、契約トラブルや瑕疵による訴訟、仲介業者とのすれ違いなど、見えないリスクが潜んでいます。この記事では地域密着で「地域未来牽引企業」に選定されたハイコム不動産の監修のもと、代表的なトラブル事例とその防止策、相談先、安心して任せられる不動産会社の選び方まで詳しく解説します。
目次
不動産売却で起こる代表的なトラブルとは?

| トラブルカテゴリ | 相手 | 主な事例 |
|---|---|---|
| 契約関連 | 買主 | ローン不成立、手付解除 |
| 金銭関連 | 不動産会社 | 仲介手数料・広告費の過大請求 |
| 物件関連 | 買主 | 瑕疵・設備トラブル・残置物 |
| 境界・権利関係 | 隣地所有者、司法書士など | 境界線不明確、埋設物 |
| 心理的瑕疵・近隣問題 | 買主 | 事故物件・トラブル未告知 |
| 仲介業者との関係 | 不動産会社 | 囲い込み、説明不足 |
不動産売却は多額の資金が動く取引であり、法律や専門知識も求められるため、一般の方にとっては見えにくい落とし穴が多数あります。ここでは、実際によく発生する7つの代表的なトラブルについて、内容と注意点を解説します。
仲介手数料や広告費のトラブル
仲介手数料に関するトラブルは、不動産会社との間で起こりやすい典型例です。特に注意したいのが「想定外の広告費請求」や「仲介手数料の二重請求」です。宅地建物取引業法では上限が定められているものの、口頭のやりとりだけで進めた結果、不要な費用を請求されてしまうことがあります。
対策:媒介契約の内容と費用項目は書面で確認し、署名・捺印前に不明点をすべてクリアにしておきましょう。
契約解除やローン不成立によるトラブル
売買契約を結んだ後に、買主の住宅ローン審査が通らず契約解除されるケースもあります。買主はローン特約がある場合は解除されても違約金は発生しませんが、売主にとっては時間や他の購入希望者を失うリスクが大きいです。
対策:契約時には「ローン特約の白紙解除の期限」「手付解除条項」などを明確にしておきましょう。
瑕疵の告知漏れと損害賠償請求
売却後に買主が「雨漏り」「シロアリ被害」「地中埋設物の発見」などを理由に損害賠償を請求するケースがあります。これは2020年の民法改正により「契約不適合責任」として売主に一定の責任が生じるため、注意が必要です。
対策:既知の欠陥は「物件状況確認書」や「告知書」に正確に記載し、住宅診断も検討しましょう。
土地の境界・埋設物など現況確認に関する問題
土地の境界線が曖昧なまま売却を進めると、隣地所有者とトラブルになる恐れがあります。また、工事中にコンクリートガラや古い配管などの地中障害物が見つかるケースもあります。
対策:測量図や登記簿の確認を怠らず、可能なら「確定測量」を行うと安心です。
設備・残置物の引渡し後のトラブル
売主が置いていったエアコンや家具などを巡って、「話が違う」「撤去してほしい」といった苦情が買主から入ることもあります。とくに残置物や設備の動作確認を怠った場合に多発します。
対策:「付帯設備表」や「残置物リスト」を活用し、双方で内容を確認した上で記名・押印を行うことが大切です。
近隣トラブルや心理的瑕疵の未告知
過去に起きた自殺や事件、あるいは近隣住民との深刻なトラブルなどは、いわゆる「心理的瑕疵」として扱われ、告知義務が発生します。未告知だった場合、損害賠償のリスクがあります。
対策:事実関係は正直に伝える姿勢が重要です。曖昧な情報でも、念のため不動産会社に共有しておくべきです。
仲介業者による囲い込みや説明不足
悪質な不動産業者が「両手仲介」によって自社利益を優先し、他社からの購入希望者をブロック(囲い込み)することもあります。また、重要事項説明や契約内容の説明が不十分だったことで紛争に発展することもあります。
対策:実績・口コミ・担当者の対応を事前に確認し、必要に応じて複数社に相談することがリスク回避につながります。
あわせて読みたい


不動産売却にかかる平均期間はどれくらい?売却が長引く原因と早く売るためのコツを徹底解説
不動産売却にはどれくらい時間がかかるのか――これは売却を検討する多くの方に共通する不安です。 一般的な売却期間の目安は3〜6ヶ月ですが、物件種別や地域、価格設定に…
トラブルの主な原因と発生しやすいタイミング

不動産売却におけるトラブルは、偶然起きるものではなく、たいてい明確な原因があります。また、それぞれの原因は売却のどの段階で起こりやすいかが分かっていれば、事前にリスクを回避できます。ここでは、売却プロセスごとの注意ポイントを踏まえ、トラブルの主な原因を整理します。
売却活動前の準備不足
もっとも多い原因の一つが「準備不足」です。相場調査や物件の状態確認をせずに売却に踏み切ってしまうと、「査定価格が想定と大きく異なる」「契約書に記載すべき告知事項が漏れる」など、初期段階から問題を抱えることになります。
タイミング:売却準備〜媒介契約の締結前
対策:複数社の査定結果を比較し、売却方針や最低希望額を事前に明確にしておきましょう。
媒介契約・販売活動中の情報伝達不足
媒介契約後、販売活動に移る段階でもトラブルは発生しやすくなります。特に「広告内容との不一致」「見学希望者への対応トラブル」などはこのフェーズに集中します。不動産会社との情報共有不足が主な原因です。
タイミング:媒介契約締結後〜購入申込前
対策:週単位で進捗確認を行い、販売状況や反響を把握できる環境を整えましょう。
売買契約時の確認漏れ
契約書や重要事項説明書の確認が甘いと、後になって「そんなこと聞いていなかった」「書類に書かれていない」という事態になりかねません。売買契約は法的拘束力が強いため、ここでのミスは重大なトラブルに発展します。
タイミング:購入申込〜売買契約締結時
対策:重要事項説明時には録音を取る・複数人で確認するなど、客観的な記録を残すと安心です。
引渡し前後の認識ズレ
設備の不具合や残置物の有無など、引渡し前後には細かな調整が必要です。口頭のみでおこなってしまった場合、「売主は撤去済みと思っていた」「買主は使える設備だと考えていた」といったズレが頻発します。
タイミング:契約締結後〜物件引渡し前後
対策:チェックリストを活用し、売主・買主の双方で合意した項目を明文化しておきましょう。
事例から学ぶ!不動産売却で実際にあったトラブルケースとその教訓
実際に起こった不動産売却のトラブル事例を知ることで、読者自身が抱える不安や疑問を明確にし、回避策を講じることが可能になります。以下では、売却の各ステージで発生しがちな典型的なトラブルと、それぞれの教訓を紹介します。
ケース1:契約不適合責任による損害賠償請求
築30年以上の中古住宅を売却したAさんは、設備の状態について「使用に問題なし」と説明して契約しました。しかし、引渡し後に雨漏りが発覚し、買主から修繕費として100万円超の損害賠償を求められました。
教訓:目に見えない不具合でも、認識していた場合は「契約不適合責任」に問われる可能性があります。売却前にホームインスペクション(住宅診断)を受け、報告書を交付するなど、客観的な情報提供が有効です。
ケース2:口約束と契約書の内容が異なりトラブルに
Bさんは不動産会社との会話で「仲介手数料は半額になる」と説明を受けましたが、契約書には通常通りの手数料が記載されており、引渡し後に請求トラブルに発展しました。
教訓:どんなに親身な営業担当でも、書面に記載されていない条件は法的には効力を持ちません。大事な話はすべて「書面化」して残すことが基本です。
ケース3:境界トラブルが発覚し引渡し延期に
Cさんは相続した土地を売却しましたが、隣地との境界線が確定しておらず、買主が引渡しを拒否。最終的には測量費用と境界確定費用をCさん側が負担する形で、2か月遅れの引渡しとなりました。
教訓:土地売却では境界トラブルが頻出します。売却前に「筆界確認書」「確定測量図」の用意ができているかを確認し、不明確であれば測量士への相談が必須です。
こうした事例からも、不動産売却では「ちょっとした確認不足」が大きなトラブルに直結することが分かります。では、どうすれば事前にこれらのリスクを防げるのでしょうか?ここでは、売主自身ができる7つの具体的な対策をご紹介します。
トラブルを防ぐために売主ができる7つの対策
不動産売却のトラブルは、「知っていれば避けられた」ものが少なくありません。事前に適切な対策を講じることで、リスクを最小限に抑え、安心して売却手続きを進めることが可能になりますので売主が実践すべき具体的な7つの対策を解説します。

1.売却前に物件状況を把握する(インスペクション)
建物の劣化や瑕疵を事前に把握することで、後の損害賠償リスクを大幅に減らせます。特に中古住宅では、ホームインスペクション(住宅診断)の実施が重要です。報告書を買主に提示することで、信頼性の高い情報提供ができ、後々の「知らなかった」というトラブルへの発展を防げます。
2.売買契約書と重要事項説明書を細部まで確認する
契約関連トラブルの多くは「内容の誤認」に起因します。不明点はすぐに宅建士や担当者に質問し、納得した上で署名することが不可欠です。また、口頭のやり取りも書面で残しておく習慣をつけましょう。
3.境界線や権利関係を事前に整理しておく
土地の売却では境界線の未確定や共有持分の存在がトラブルの火種になりがちです。必要に応じて土地家屋調査士や司法書士の協力を得て、名義・境界・権利関係を整理しておくことで交渉がスムーズに進みます。
4.買主への告知義務を誠実に果たす
心理的瑕疵や環境的瑕疵(騒音・近隣トラブルなど)は、曖昧にせず正確に告知する必要があります。「隠した方が得」は結果的に損失を招くことも。信頼こそがトラブル防止の鍵です。
5.契約不適合責任の内容を理解しておく
民法改正により、売主の責任範囲が広がっています。契約不適合責任は、「知らなかった」では通用しない場合もあります。責任の所在や範囲を正確に理解し、必要に応じて免責特約を盛り込むことも検討しましょう。
6.仲介業者とのやり取りは必ず書面に残す
トラブルの多くは「言った・言わない」問題です。仲介手数料や広告費の請求条件、査定価格の根拠なども、メールやLINE、契約書で証拠を残すようにしてください。
7.信頼できる不動産会社を選ぶ
囲い込みや説明不足、強引な営業が原因のトラブルも後を絶ちません。売却実績・担当者の対応・口コミなどをしっかり確認し、「納得できる相手に任せる」ことがトラブル防止の最初の一歩です。
これらの対策を講じることで、多くのトラブルは未然に防ぐことができます。しかし、万が一トラブルが発生してしまった場合は、どこに相談し、どのように対応すればよいのでしょうか?次章では、実際に頼れる相談先や解決の手順について詳しく解説します。
万が一に備えて知っておきたい!不動産売却トラブルの相談先と解決手段
どれだけ注意を払っていても、トラブルが完全に防げるとは限りません。不動産売却は高額で専門的なやり取りを伴うため、万が一の備えとして「どこに相談すべきか」「どのような解決方法があるのか」を知っておくことが非常に重要です。
公的な相談機関に相談する
まずは中立的な立場でアドバイスをくれる公的相談窓口を活用しましょう。
- 国民生活センター(消費者ホットライン):188(局番なし)で全国共通。消費者トラブル全般に対応。
- 地方自治体の消費生活センター:住んでいる地域ごとに相談窓口があり、身近な助言を受けられます。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO):不動産取引に関する苦情・紛争の調整制度あり。
宅建協会や不動産会社の相談窓口を活用する
不動産会社とのトラブルは、まず契約した会社の営業責任者や相談窓口に状況を伝えましょう。誠意のある企業であれば、速やかな対応が期待できます。また、加盟している宅建協会(全日本不動産協会・全国宅地建物取引業協会など)に申し立てを行うことも可能です。
専門家(弁護士・司法書士・税理士)に相談する
法的対応が必要な場合は、専門家への相談が不可欠です。
例えば、
- 契約不適合責任に関する損害賠償請求
- 境界線の争いに関する調停・訴訟
- 契約解除や手付金の返還問題 など
初回無料相談を実施している法律事務所も多いため、気になるトラブルがあれば早めに連絡することが肝心です。
トラブル発生後の基本的な対応フロー
- 事実関係の整理:契約書・メール・LINEなど証拠を手元にまとめる
- 一次対応:相手方(不動産会社・買主)に誠意をもって連絡
- 専門家や第三者機関に相談:状況に応じて法的手段の準備も検討
このように、相談先と手順を知っておくことは「最大の安心材料」です。
まとめ|不動産売却トラブルを防ぐ最大のカギは「信頼できるパートナー選び」
不動産売却は人生で何度もあることではなく、ほとんどの人が初心者です。そのため、知識不足や思い込みからトラブルに発展するケースが後を絶ちません。
本記事で解説したように、売却時には以下のような点に注意が必要です。
- 契約・金銭・物件にまつわる代表的なトラブルの理解と対策
- トラブルが起きたときの相談先と対応の流れ
- 安心できる不動産会社の見極める
つまり、トラブルの大半は「事前の備え」と「信頼できるパートナー選び」で防げるのです。
熊本市で不動産売却を検討している方は、地元密着・宅地建物取引士多数在籍のハイコム不動産にぜひご相談ください。
✅売却/買取/リースバック/賃貸、4パターン同時査定で最適提案
✅最短即日のスピード査定
✅買取保証付きで「売れ残りリスク」を回避
✅相続・離婚・ローン滞納などセンシティブな相談も秘密厳守で対応
大切な不動産を安心して売却するためにも、「よくある失敗」を自分のこととしてとらえ、後悔のない売却を実現しましょう。
▶不動産売却の失敗例に学ぶ注意点!後悔しないために避けるべき5つの落とし穴とは?
📞まずは無料相談からお気軽にどうぞ
TEL:0120-8156-87