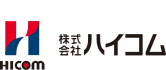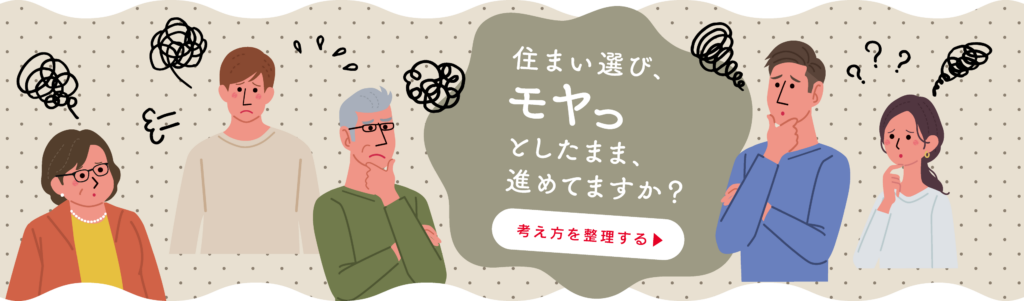
相続で不動産を取得したものの、「売りたいけれど手続きが複雑そう…」と悩む方は多いのではないでしょうか。
名義変更や相続登記、税金の申告など、通常の不動産売却と比べてやるべきことが多いため、正しい手順を知っておくことが大切です。
この記事では、熊本市を中心としたエリアの賃貸・売買物件を豊富に取り扱っている【ハイコム】監修の下、相続不動産をスムーズに売却するための流れと必要書類、注意点をわかりやすく解説します。(2025年現在の情報です。)
目次
相続した不動産を売却する前に確認すべき3つのこと

相続した不動産を売却するには、通常の売却とは異なる準備が必要です。特に相続登記や権利関係が整理されていないまま売却を進めようとすると、手続きが進まず時間と費用がかかるリスクもあります。ここでは、売却の前に必ず確認しておきたい3つのポイントを解説します。
不動産の名義は相続登記されているか
不動産を相続した場合、まず行うべきなのが相続登記(名義変更)です。
故人名義のままでは売却はできず、登記簿上の所有者が申請者であることが必須条件となります。
相続登記は2024年4月以降、原則義務化されており、3年以内に登記を申請する義務がありますので、放置すると過料の対象にもなり得ます。
売却前には、「誰がその不動産を所有することになったのか」を登記簿で明確にし、その上で売却を進める必要があります。
遺産分割協議は済んでいるか
相続人が複数いる場合、相続登記を行うには遺産分割協議書の作成と全員の合意が必要です。
この協議がまとまっていない状態では、売却の手続き自体ができません。
たとえば兄弟間で「住む・売る・保有する」の意見が分かれていると、登記が進まず、売却にも大きな支障が出ます。
また、協議書の内容は後に税務処理にも影響するため、できるだけ早めに協議をまとめ、書面化しておくことが大切です。
売却できる状態かどうか(共有名義・空き家等)
相続不動産はしばしば「共有名義」「老朽化した空き家」「田畑や山林」など、特殊な状態にあることが多くあります。
売却前には、その不動産が「今すぐ売れる状態かどうか」を客観的に確認する必要があります。
- 共有名義 → 全員の同意が必要
- 空き家 → 建物の状態により解体が必要な場合も
- 農地 → 所有権移転や用途変更に制限あり
あわせて読みたい


離婚時に不動産を売却するには?財産分与・住宅ローン・名義変更の進め方を解説
離婚を機に、夫婦共有の住宅をどうするか悩んでいませんか?売却する場合、「名義変更は必要?」「住宅ローンはどうなる?」「売却代金はどう分けるのか」など、考慮す…
相続不動産の売却で必要な名義変更と手続きの流れ
不動産を相続したからといって、すぐに売却できるわけではありません。まず必要なのが「相続登記(名義変更)」の完了です。この手続きを経なければ、法的に売却する権利を持つことができません。ここでは、相続登記の概要と注意点について解説します。
相続登記の基本と必要書類
相続登記とは、不動産の所有権を故人から相続人に移す手続きです。登記を完了させるには、以下の書類が必要になります。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全て)
- 相続人全員の戸籍・住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(共有名義の整理が必要な場合)
- 登記申請書(法務局提出用)
これらの書類を揃えて法務局に申請することで、正式に売却できる状態になります。
参照:法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」
登記が未完了の場合の影響と注意点
登記が未完了のままでは、不動産の所有権は法的に相続人に移転していないとみなされます。そのため、売却契約の締結ができず、買主への引渡しも不可能です。
また、登記義務化以降は放置していると過料が発生するリスクもあるため、速やかな対応が求められます。特に相続人が複数いる場合は、登記前の話し合いが長期化することもあるため、計画的に進めましょう。
司法書士に依頼する場合の費用と期間
登記手続きは自分で行うことも可能ですが、専門知識が必要なため、多くの場合は司法書士に依頼します。費用相場は、1件あたり5万〜10万円程度+登録免許税(不動産評価額の0.4%)が目安です。
登記完了後にできること
登記が完了すると、相続人が正式な所有者として登記簿に記載されます。この状態になって初めて、以下のような手続きが可能となります。
- 不動産会社への売却依頼(査定・媒介契約など)
- 売買契約の締結と決済
- 確定申告や税務申告での名義証明
つまり、登記完了がすべての出発点となるため、売却前の最重要ステップといえるでしょう。
売却手続きのステップを順に解説
相続した不動産の売却は、通常の売却と比べて手順が多く、準備も複雑です。ここでは、相続登記完了後の売却までの一連のステップを時系列でわかりやすく解説します。
不動産会社に査定を依頼する
相続登記が完了したら、まずは不動産会社に査定を依頼します。
査定には「机上査定(簡易)」「訪問査定(現地調査)」の2種類があり、相続物件は現況が放置されていたり老朽化していたりするケースも多いため、訪問査定が推奨されます。
また、複数社に査定を依頼し、提案内容や対応の誠実さも含めて比較することが重要です。
遺産分割協議書に基づき売却を進める
複数人で相続した不動産を売却する場合、「誰が売却手続きを行うか」「売却代金をどう分けるか」などの取り決めが必要です。
これらは遺産分割協議書で事前に明文化しておくことで、手続きの円滑化と税務上のトラブル防止につながります。
媒介契約〜売買契約の流れ
売却活動は、媒介契約(専属専任・専任・一般)を結ぶことで正式にスタートします。
その後、購入希望者が現れた段階で価格交渉を行い、売買契約の締結へと進みます。
売却代金の分配と税務処理
また、譲渡所得が発生する場合は翌年の確定申告が必要となるため、税理士のサポートを受けながら適切に処理しましょう。

相続した不動産を売却する際の税金と控除制度
相続した不動産を売却するときには、譲渡所得税の申告が必要になる場合があります。
また、条件を満たせば「取得費加算の特例」や「3,000万円控除」といった節税制度が活用できるため、事前に仕組みと条件を理解しておくことが大切です。
譲渡所得税とその計算方法
不動産を売却して得た利益は「譲渡所得」として課税対象となります。
譲渡所得は以下の式で計算されます:
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用)
相続で取得した不動産の場合、被相続人が当初購入した際の取得費がわからないこともあります。その場合は概算取得費(売却価格の5%)で計算されますが、税額が高くなる可能性があります。
そのため、購入時の契約書や領収書などが残っていれば、実額での申告が可能かどうかを確認することをおすすめします。
取得費加算の特例とは
相続税を支払った不動産を一定期間内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」が使えます。
これにより、譲渡所得が減少し、結果的に所得税・住民税の負担を軽減できる可能性があります。
この特例の適用には、以下の要件を満たす必要があります
- 相続開始から3年10ヵ月以内に売却すること
- 相続税の納税が完了していること
- 相続人がその不動産を売却すること
3,000万円控除との併用可否
相続した家屋に被相続人が住んでいた場合、条件を満たせば「被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除」が使えることがあります。
これは、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度であり、非常に大きな節税効果があります。ただし、取得費加算の特例との併用はできないため、どちらを選ぶべきか慎重に判断する必要があります。
どちらの制度が有利かは、税理士に試算を依頼するのが確実です。
参照:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
あわせて読みたい


不動産売却で使える控除まとめ!3,000万円特別控除・相続・買換えの節税制度を解説
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税が課税されます。ですが、「3,000万円の特別控除」や「相続の取得費加算」などの制度を使えば、大幅に節税できることも。こ…
確定申告が必要になるケース
譲渡所得が発生した場合は、翌年の2月16日〜3月15日までに確定申告が必要です。
特に控除制度を使うためには、確定申告書に加え、売買契約書・登記事項証明書・相続税申告書の写しなどの添付が求められます。
申告を怠ると、延滞税や無申告加算税が発生するため、売却益が出た場合は早めに税務の準備を始めることが重要です。
相続不動産売却に関する節税制度比較表
| 制度名 | 控除額 | 適用条件 | 他制度との併用可否 | 申告の必要性 |
|---|---|---|---|---|
| 取得費加算 | 相続税の一部 | 相続から3年10ヵ月以内 | × | 要 |
| 3,000万円控除 | 最大3,000万円 | 被相続人の居住用 | × | 要 |
相続不動産の売却でよくあるトラブルと対策
相続した不動産の売却には、法的・心理的な要素が多く関わるため、一般的な売却よりもトラブルが起きやすい傾向にあります。ここでは、実際によくあるトラブルとその対策を具体的に紹介します。
遺産分割でもめて売却できない
相続人同士で「誰が所有するか」「売るか貸すか」などの意見が対立し、遺産分割協議がまとまらないまま時間だけが過ぎるというケースがよくあります。
協議が成立しなければ、相続登記も売却も進めることができません。
対策としては、感情的な対立を避けるために、司法書士や弁護士を交えて早期に第三者の調整を取り入れることが有効です。将来的に調停や審判になる前に、書面で合意形成を図ることが重要です。
登記手続きに時間がかかる
登記に必要な書類の準備や取得が遅れたり、登記を依頼した司法書士の対応が滞ったりして、売却のタイミングを逃すケースもあります。
特に被相続人の戸籍が各地に点在している場合、取得に数週間〜1ヵ月以上かかることもあり得ます。
対策としては、必要書類のリストを早期に確認し、司法書士に早めに相談しておくことが肝心です。
売却後の税金申告を忘れていた
売却後の確定申告を忘れると、延滞税やペナルティが発生します。特に、「譲渡益が出ていないから関係ない」と誤解して申告を怠るケースは少なくありません。
空き家として放置して固定資産税が増加
売却までの間に不動産を空き家のまま放置していると、特定空き家に指定され、土地の資産税が6倍になるケースもあります。
また、防犯や火災リスクも高まるため、売却までの間も適切な管理やメンテナンスを行う必要があります。
空き家管理サービスの利用や、地元の不動産会社との連携で「売却前提の短期賃貸」なども検討できます。
熊本市で相続不動産の売却をするなら

相続不動産の売却は、地域の不動産市況や法務・税務の知識が必要なため、全国対応のサービスよりも、地元に強い不動産会社を選ぶのが得策です。ここでは熊本市で相続物件をスムーズに売却するために押さえておきたいポイントをご紹介します。
地域の相続事例に詳しい業者を選ぶ
熊本市内でも、中央区・東区をはじめとするエリアごとに地価動向や人気のエリア、取引慣行には違いがあります。
特に相続物件は築年数が古かったり、空き家期間が長いなど市場評価に差が出やすいため、地域での売却実績や相続関連の取り扱い経験が豊富な業者に依頼することが大切です。
税理士・司法書士と連携できるか
相続不動産の売却は、名義変更・登記・譲渡所得の確定申告など、法務・税務の専門手続きが不可欠です。
そのため、社内または提携ネットワークに司法書士や税理士がいる業者は、相談から手続きまで一括で対応してもらえる安心感があります。
売却後のアフターサポートまで相談可能か
売却後には、確定申告のサポートや引越し、空き家管理、残置物の処分などが必要になるケースもあります。
熊本市内の不動産会社の中には、これらのアフターケアを含めたトータルサポートを提供している業者も存在します。
まとめ
相続不動産の売却は、通常の売却とは異なり、名義変更や税務手続き、相続人間の調整など、事前にクリアすべきハードルが多く存在します。
「登記が終わっていない」「協議がまとまらない」「税金の申告を忘れていた」など、対処が遅れると売却のチャンスを逃してしまうことにもつながります。
そのため、まずは相続登記と遺産分割の手続きから確実に進め、そのうえで信頼できる不動産会社と連携することが、トラブルのない売却成功への近道です。
熊本市内で相続した不動産を売却するなら、地域に根差し、税理士・司法書士とのネットワークを活かした対応ができる仲介業者を選ぶことが、安心と納得の鍵になります。
不安や疑問がある方は、早めに専門家へ相談し、余裕を持って準備を進めましょう。