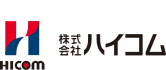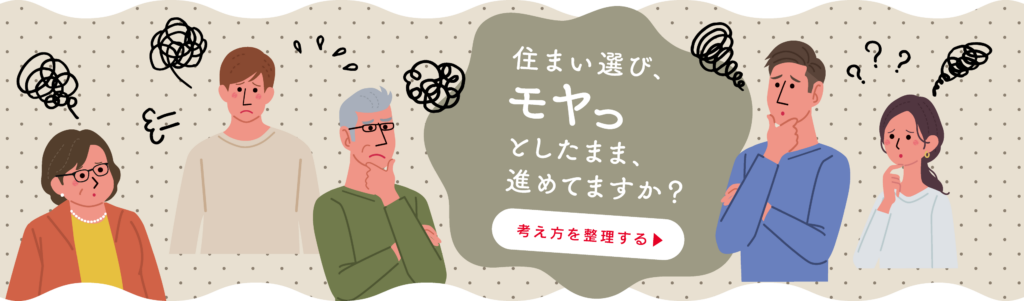
不動産を売却しようとしたとき、「名義が自分以外のままでは売れないのでは?」と悩む方は少なくありません。特に以下のような不安を抱えるケースが多くあります。
- 相続登記が済んでいない実家を売却したい
- 夫婦共有名義の不動産をどう処理すべきか分からない
- 離婚や抵当権が絡む場合の手続きが複雑そうで不安
この記事では、不動産売却に伴う名義変更の基本から流れ、必要書類や費用、さらに相続・共有・離婚などケース別の注意点まで整理して解説します。読めば、不動産売却時の手続きを正しく理解し、安心してスムーズに進められるようになります。
目次
不動産売却と名義変更の基礎知識
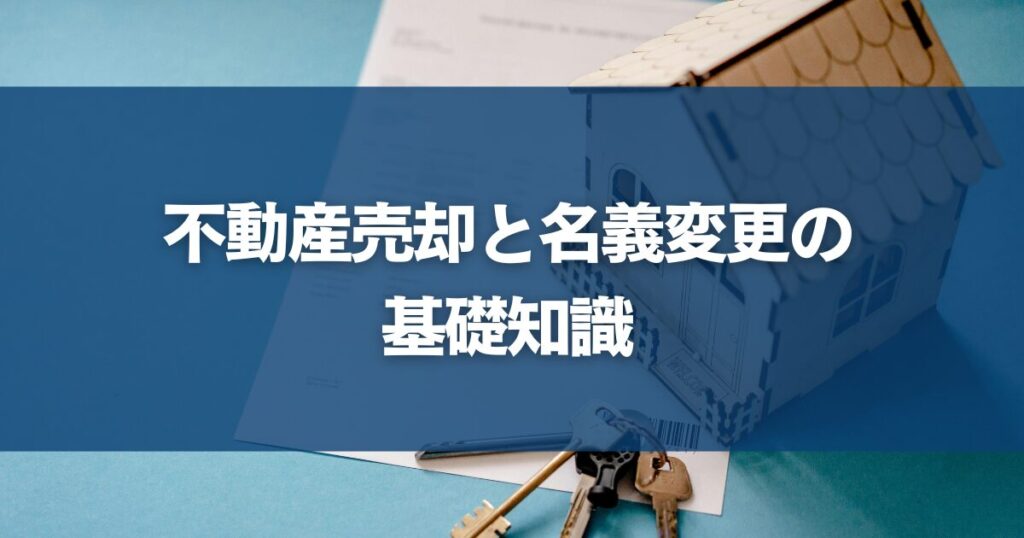
名義変更とは何か
不動産を売却する際に避けて通れないのが「名義変更」です。ここでいう名義変更とは、登記簿上の所有者を実際の売買や相続の内容に合わせて変更する手続きを指します。不動産の所有権は売買契約の成立により当事者間で移転します。ただし、登記を行わないと第三者に対抗できず、実務上は決済・引渡しと同時に登記申請を行うのが必須です。
名義変更が必要となる主なケース
名義変更が必要となるケースは複数あります。典型的なのは売買ですが、相続による名義変更や、離婚後の財産分与による名義変更、贈与による名義変更もあります。特に相続登記は2024年から義務化されており、未了のまま放置すると過料の対象になることが定められています。そのため、名義変更の正しい理解は不動産売却を成功させるうえで欠かせません。
名義変更をしないと起こるトラブル
名義変更をしないまま売却を進めると、以下のようなトラブルに直面する可能性があります。
- 売買契約が締結できない
- 相続人間での権利争いが起こる
- 抵当権や差押えが残り、買主が不安を抱く
このように、名義変更は「売却の前提条件」であり、売主にとっても買主にとっても安心して取引を行うための必須手続きなのです。次では、その流れを具体的に確認していきましょう。
あわせて読みたい


相続した不動産を売却するには?名義変更・登記・税金の手続きと流れを徹底解説
相続で不動産を取得したものの、「売りたいけれど手続きが複雑そう…」と悩む方は多いのではないでしょうか。名義変更や相続登記、税金の申告など、通常の不動産売却と比…
不動産売却で名義変更を行う流れ
【図解】不動産売却で名義変更を行う流れ
売買契約の締結
不動産会社や直接取引を通じて契約書を交わす。
→
決済準備
残代金支払・ローン残債確認・抵当権抹消などを実施。
→
所有権移転登記の申請
司法書士が代理で登記を申請。法務局による審査あり。
→
登記完了・引渡し
決済日に引渡しと同時に登記申請。完了まで約1週間。
不動産売却に伴う名義変更は、主に以下の流れで行われます。
- 売買契約の締結
不動産会社の仲介や直接取引を通じて売買契約書を交わします。この時点で、売主と買主双方の権利義務が明確になります。 - 決済準備
契約後、残代金の支払いや住宅ローンの残債確認、抵当権の抹消手続きが行われます。司法書士がここで中心的な役割を担い、必要書類を確認していきます。 - 所有権移転登記の申請
所有権移転登記は共同申請が原則ですが、実務では司法書士による代理申請(オンライン含む)が一般的で、当事者が法務局に出向く必要はほとんどありません。 - 登記完了・引渡し
通常は決済日に、残代金の支払い・物件引渡し・所有権移転登記の申請を同時に行います。登記の完了はその後1週間程度かかります。
所有権移転登記の申請
名義変更の流れを理解するうえで、特に重要なのは「法務局での登記申請」です。法務局への申請は登記官が審査を行うため、不備があれば差し戻しになることもあります。そのため、司法書士を通じて行うのが一般的です。
登記完了と引渡し
登記完了までは通常1週間前後ですが、法務局の混雑や補正の有無により前後します。各法務局の完了予定日を確認しておきましょう。売却全体のスケジュールを立てる際には、この期間を見込んでおくことが大切です。続いては、実際に名義変更に必要となる書類と費用を見ていきましょう。
名義変更に必要な書類と費用相場
不動産売却に伴う名義変更を進めるには、複数の書類を揃える必要があります。売主・買主の双方に必要な書類があり、ケースによって追加書類が求められる点に注意が必要です。
名義変更に必要な基本書類
代表的な書類には以下のものがあります。
- 登記識別情報(または登記済権利証)
- 印鑑証明書
- 住民票
- 売買契約書
- 固定資産評価証明書
相続が絡む場合は、これに加えて戸籍謄本、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図などが必要です。離婚による財産分与の場合は、財産分与契約書や調停調書が求められるケースもあります。
名義変更のための費用は主に2つ
不動産の所有権移転登記(いわゆる名義変更)には、大きく分けて「登録免許税」と「司法書士報酬」が発生します。
売買による所有権移転登記の登録免許税は、原則2.0%(1000分の20)です。
土地については令和8年(=2026年)3月31日までの特例措置により1.5%(1000分の15)に軽減されています。
一方で、相続による移転は0.4%(1000分の4)が原則ですが、財産分与(特に離婚に伴うもの)などの一部ケースでは「その他の原因」として2.0%が適用される場合もあります。
例えば、評価額が2,000万円の土地を相続で取得した場合は、登録免許税は約8万円(0.4%)です。
一方、売買の場合は本則2.0%で約40万円、軽減特例(1.5%)が適用される場合は約30万円となります。
司法書士報酬は事務所により異なりますが、報酬は自由化されており、おおむね5万〜15万円程度の範囲で設定されることが多いです。
そのほか、印鑑証明書・戸籍(全部事項)証明書・固定資産評価証明書などの取得手数料も必要です。
これらは1通あたり300〜450円程度が目安で、通数によっては数千円〜数万円の追加費用が発生します。
一般的に、所有権移転登記費用は買主負担、抵当権抹消登記など既存負担の解消費用は売主負担とする契約が多く採用されています。
契約前に司法書士や不動産会社に確認し、費用分担を明確にしておくことがトラブル防止につながります。
共有名義不動産の売却と名義変更の注意点
不動産売却の名義変更の際に、特に多くの相談が寄せられるのが**「共有名義の不動産」**です。
共有名義とは?
共有名義とは、夫婦・兄弟・親子など複数人が一つの不動産を共同で所有している状態を指します。登記簿には各人の「持分割合」が記載され、所有権が分割されているのが特徴です。たとえば、夫婦で2分の1ずつの持分を持つケースや、相続で複数人に分割されるケースが典型例です。
共有名義は柔軟に財産を保有できる反面、売却や名義変更の際には大きな制約が発生します。
共有名義不動産を売却するための条件
共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意が不可欠です。1人でも反対すれば売却は成立しません。また、名義変更(所有権移転登記)を行う際も、共有者全員が登記に関与する必要があります。
このため「遠方に住む兄弟が連絡に応じない」「意見がまとまらない」といったケースでは、売却が長期化するリスクがあります。事前の合意形成と調整が最も重要なポイントです。
共有持分だけを売却する方法
共有者の1人が「自分の持分だけ売却したい」と考える場合、共有持分のみを第三者に売却することは可能です。ただし、買主は共有持分だけを取得しても自由に利用できないため、通常は買取専門業者などが購入するケースが中心となります。
この場合、売却価格は市場価格より大幅に下がる傾向があり、他の共有者との関係が悪化するリスクもあります。慎重に検討することが求められます。
トラブルを避けるための対応策
共有名義不動産の売却では、トラブル防止が最大の課題です。特に相続で複数の相続人が共有名義になった場合、利害関係の調整は難航しやすくなります。トラブルを避けるためには、以下の対応が有効です。
- 事前に全員で売却方針を明確にして合意を形成する
- 遠方に住む共有者とは書面で合意を残す
- 司法書士や弁護士など専門家を交えて公平性を担保する
こうした対応を取ることで、共有者間の感情的な対立や契約不履行のリスクを大幅に減らせます。
共有名義の選択肢
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 全員合意で売却 | ・市場価格に近い価格で売却できる・買主も安心して購入できる | ・共有者全員の同意が必要・合意形成に時間がかかる場合がある |
| 持分のみ売却 | ・他の共有者の同意が不要・早期に現金化できる | ・市場価格より安くなる・第三者が共有者となりトラブル化しやすい |
相続・離婚・抵当権付きなどケース別の名義変更の注意点
不動産売却における名義変更は、状況によって必要な手続きや書類が大きく異なります。代表的なケースごとに整理して確認してみましょう。
気をつけるべき点
相続登記が未了の場合
親や祖父母などが亡くなったまま相続登記をしていない不動産は、そのままでは売却できません。法定相続人全員の合意を取り付け、遺産分割協議書を作成し、相続登記を完了させる必要があります。2024年以降は相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると過料が科される可能性があるため、早めの対応が必須です。
離婚による財産分与後の売却
離婚の際に不動産を財産分与の対象とした場合、分与を受けた側が単独名義に変更したうえで売却するのが一般的です。財産分与契約書や調停調書が必要になることが多く、司法書士の関与が欠かせません。
抵当権が残っている場合
抵当権が残ったままでも売却契約自体は可能ですが、引渡しまでに残代金でローンを完済し、抵当権抹消登記を行うのが通常です。金融機関との調整を行い、売却代金でローンを完済し、同時に抵当権抹消登記を行う流れになります。
これらのケースごとの注意点を理解しておくことで、予想外のトラブルを回避できます。
名義変更を依頼できる専門家と役割について
名義変更の手続きは法務局に申請すれば自分で行うことも可能ですが、実際には専門家に依頼するケースが大半です。その理由は、手続きが複雑で書類不備のリスクが高いためです。
司法書士
所有権移転登記の申請を代行できるのは司法書士です。登記に必要な書類の確認や申請手続きの代行、登記完了後の証明書取得まで幅広くサポートしてくれます。費用は5万〜10万円程度が目安ですが、確実に登記を完了できる安心感があります。
不動産会社
不動産会社自体が登記手続きを行うことはできませんが、提携する司法書士を紹介してもらえるのが一般的です。売買契約から登記、引渡しまでの全体スケジュールを一括で管理してもらえるのは大きなメリットです。
弁護士・税理士
相続人同士のトラブルや離婚時の財産分与に関する紛争がある場合は、弁護士の関与が必要です。また、相続税や譲渡所得税の計算に関しては税理士のサポートが役立ちます。複数の専門家が連携することで、法律・税務・実務のすべてをカバーできます。
不動産売却は法律・税金・契約の要素が複雑に絡み合うため、専門家と早めに相談しておくことが安心につながります。次に、具体的にトラブルを避けるための実践的なポイントを見ていきましょう。
不動産売却時の名義変更でトラブルを避けるポイント
名義変更の場面では、思わぬトラブルが発生することがあります。特に相続や共有不動産では利害関係が複雑になりやすいため、以下のポイントを押さえておくと安心です。
- 必要書類を事前に揃えておく
- 相続人や共有者との合意を早めに整える
- 司法書士や弁護士への相談を早めに行う
- 登記の申請期限や法改正(相続登記義務化)に注意する
これらを徹底することで、登記の差し戻しや相続人間の対立といったトラブルを未然に防ぐことができます。トラブル回避の観点からも、専門家の関与は極めて重要です。次では、熊本で実際に相談する場合の地域密着型サポートについて紹介します。
あわせて読みたい


不動産売却の登記変更完全ガイド|所有権移転登記の流れ・必要書類・費用と注意点
不動産を売却する際に欠かせないのが所有権移転登記です。所有権の取得自体は契約で生じ、登記は第三者に対抗するために必要です。 しかし、多くの方が次のような疑問を…
熊本で不動産売却に関わる名義変更手続きを進めるには
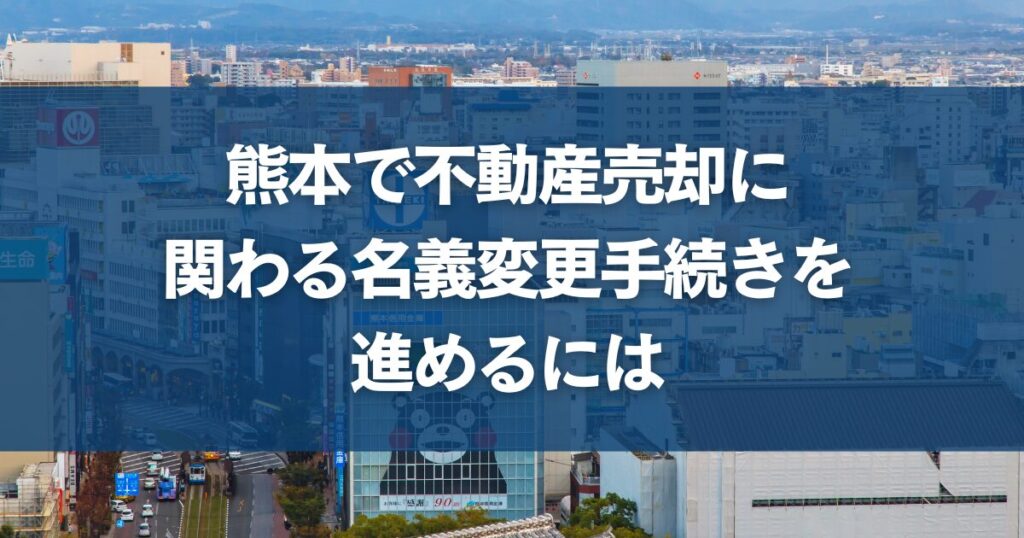
全国的な制度や登記方法は同じでも、地域によって不動産売却の進め方や買主の動向は異なります。熊本市で不動産を売却する場合は、地域事情に詳しい不動産会社に相談することが安心です。
ハイコム不動産では、査定から売却、司法書士との連携による登記支援までワンストップで対応しています。AI机上査定と現地査定を組み合わせて最短即日で売却プランを提示し、相続や離婚といった複雑なケースでも専門スタッフが寄り添ってサポートします。
さらに、売却後も買取保証や不用品引取サービスを用意しているため、売主が「売った後も安心」できる体制を整えています。熊本市で不動産売却と名義変更をスムーズに進めたい方にとって、地域密着型の窓口は大きな支えとなるでしょう。
まとめ
不動産売却における名義変更は、所有権移転登記を行うことで初めて成立します。売買契約後は法務局での登記申請が必要であり、必要書類や費用を正しく理解することがスムーズな売却の第一歩です。特に相続や共有名義、離婚といったケースでは追加の書類や合意形成が求められるため、司法書士や不動産会社のサポートを受けるのが現実的です。
熊本市で不動産を売却する際には、地域に根ざしたサポートを行うハイコム不動産に相談することで、複雑な手続きやトラブルの不安を軽減できます。安心して次の一歩を踏み出すためにも、名義変更を正しく理解し、確実に実行することが重要です。